|
�Q�D�ʁ@�u
�t���́A�b��s�̖k���A�A�������̖k���Ɉʒu���A���͓��͊����S���쒬���R�ɁA��͐�����
�R�E�����������R�ɁA���͐��������R�E�Γ�s�⍪�E���������c�ɁA�k�������S�������R�V
��E���ߍ]�s�钬�ɂ��ꂼ��אڂ��Ă��܂��B
��v���H����̋����Ƃ��ẮA�b��s���𓌐��ɑ��鍑��1�����̐M���u���k�e�v�����_����
�k��4�q���������ɂ���A���_�������H�̗����C���^�[����9�q�A����20�N�i2008�j3��23����
�J�ʂ����V���_�������H�̍b��C���^�[����14Km�A�b��E�y�R�C���^�[����17�q�A�M�y�C���^
�[����18�q�̋����ɂ���܂��B
����̎�v���H�́A�������k�ɑ��錧��164���i�����������j���c�т��ė������R�V��
�ɒʂ��A�܂��A�������̐M���u�t���v���N�_�Ƃ����_�������H�̗����C���^�[���ʂւ̓��H��
���Ĕ��c���o�R�������܂��ʂ��Ă�������165���i�t���������j���k�����ʂɐL�тĂ���A��
�N�͌�ʗʂ������A������ɂ͌�ʐM����2�J������A�ԎЉ�Ƃ͂�����ʎ��̂���������
������Ă���Ƃ���ł��B
�Ȃ��A����164�����͌��ݏt�����痳�����R�V��Ԃ��ꕔ�n���Ƃ�
���Ă��܂����A����22�N�i2010�j�ɂ͐��������ܑ��H���������̗\��ł���A��������X
�Ɍ�ʗʂ���������̂Ǝv������Ă��܂��B
|
�Q�l�j
����8�N�i1875�j12���쐬���u�t�����n���v�ɂ��ƁA
�u�����v�Ƃ��Ď��̂Ƃ���L�q����Ă��܂��̂ŁA�Q�l
�Ƃ��ċL�ڂ��܂��B
�����@���ꌧ����蓌�����n�E���������Ԏl���l��
���͊����S���R�����W�ֈ뗢�Z��
�k�����S������
�����W�ֈ뗢�Z�����Ԕ��@���S�R�m�㑺���W�ֈ뗢
�l���E�Z�ԁ@���͖{�S���c�����W�֏E�\�l��
�� ��͓��S�����R�����W�֓����\�l�ԓ��S�R����
�W�֓��뒬�O�E�Z�ԁ@���S�����w���W���뗢��
��
���S�������֎l�����@�_��S�����s���֎O����
��
�t���̌��W�́A���u�l�ҁv�i�k����������쑤�̌����_�̓�
�p�A����͎���k�p�j�ɂ���A�t���̋N�_�ł����B�R����
�W�ւ͕�����ʂ��Ă̋����ł��B
�i�Q�l�j
�ڊі@�������E�ʐς̒P�ʁA�i���A���A�ԁA��A�ځA���j
|
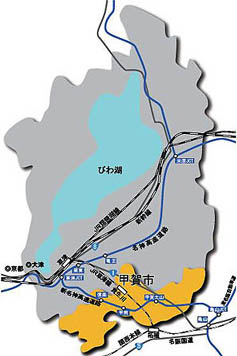 |
|
1��
|
= 36��
|
|
|
|
|
��3.927�L��Ұ��
|
|
|
1��
|
= 60��
|
= 360��
|
|
|
��109.09Ұ��
|
|
|
|
1��
|
= 6��
|
|
|
��1.818Ұ��
|
|
|
|
1��
|
= 10��
|
|
|
��3.03Ұ��
|
|
|
|
|
1��
|
= 10��
|
=
10/33Ұ��
|
��0.303Ұ��
|
|
|
|
|
|
= 1��
|
=�@1/33Ұ��
|
��3.03���Ұ��
|
���吳10�N�i1921�j�Ɏڊі@���p�~���ꃁ�[�g���@�ֈڍs����Ă��܂��B
�������A�{�i�I�ȃ��[�g���@�̕��y�́A���a26�N�i1951�j�Ƀ��[�g���@�̎g�p���`���t�����v�ʖ@��
�@�@�{�s����ł��B
�y���݂̏t���i����21�N1���j�z
|