|
戦国時代
1570年 上山城(山)は織田信長に攻め落とされる。伴氏は織田信長に仕える
1582年 伴資宗氏 本能寺にて信長と共に戦死、下山城は廃城となる。
1585年 中村一氏 水口岡山城主になる
1590年 増田長盛 同上
1595年 長束正家 同上
1600年 関が原の戦で西軍破れ岡山城落城、焼失、長束正家は日野へ落ち、妻栄子姫は
はぐれて山中をさまよい北脇へ
桜ヶ丘を通った栄子姫
山直(やまなお)の桧泉(ひのきしょうず)の水絶えず 我が長束の城は絶えにけり
水口城主(当時は古城山の上)長束正家は、関が原の戦で西軍方についたため敗北の直後
東軍に城を攻め落とされた。正家は日野へ逃げ落ちたが、臨月で身重の夫人栄子は道をあ
やまり松尾の集落から山道へと迷い込んでしまいます。その際どこをどのように通ったかは定
かではありませんが、伝承では小松尾(旧第1水口台)→畔八丁(現第四水口台)→菖蒲谷
(桜ヶ丘BCブロック付近)→千代坊(千代坊池付近)を経て伴中山方面へ出、最終的に北脇で
かくまわれ、出産後に亡くなったといわれています。
今も北脇(柏木神社の西近く)には姫塚が残っています。 |
|
江戸時代
最初期は 伴上野守資光が治める。
1602〜1682年までは幕府直轄地として代官職が置
かれる。
1624年 上山村(現山)を上村と下村に分割
1632年 小堀遠州 水口碧水城完成
1655年 八田焼き始まる。
1675年 上村を分けて、上村と堂村とする。
1682年 加藤明友 水口城主となる。 |

現在は307号線に移された芭蕉の句碑 |
|
1749年 寺子屋創業(八田村、春日村、下山村、伴中山村、山村) 明治7年ごろまで続。
八田では西栄寺、下山村では九品寺、山村では善勝寺に置かれた。
桜ヶ丘の近くを通った松尾芭蕉 〜はがれたる 身にはきぬたの ひびきかな〜
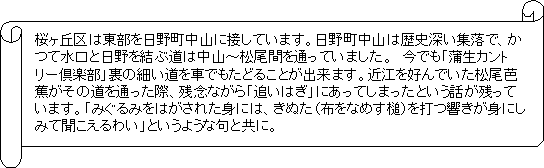
|
|
明治時代〜大正
1871年 廃藩置県 水口藩→水口県へ
1874年 明治7年 学校の設立 余力学校(伴中山、下山) 敬心学校(春日、八田) 行文学
校(山、松尾)畑村を春日村と改称
|
1875年 明治8年 上村、堂村、下村を合わせて山村と
改称
1886年 明治19年 春日尋常小学校開校、2年後に伴
谿尋常小学校と改称
1904年 明治37年 伴谷尋常小学校 現在の位置に新
築 <日露戦争勃発>
1911年 明治44年 村役場と農業組合事務所の2ヶ所
に電話開通
1913年 大正2年 各家庭に電灯つく |
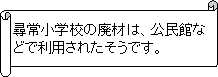
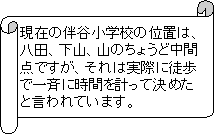 |
|
地名の移り変わり
山 上山村 → 江戸期 上村と下村に分割
→上村(東部)、堂村(山村神社付近)、下村(菅谷付近)に分割
→明治八年 三村あわせて 山村 → 山
伴中山 中山村 →中世以降 伴氏が治める中山村=伴ノ中山村 → 伴中山
下山
下山村
→ 下山
春日 畑村 → 春日村 → 春日
八田 八田村(かつては岩根郷に属する) → 八田
ページトップに戻る |
|

